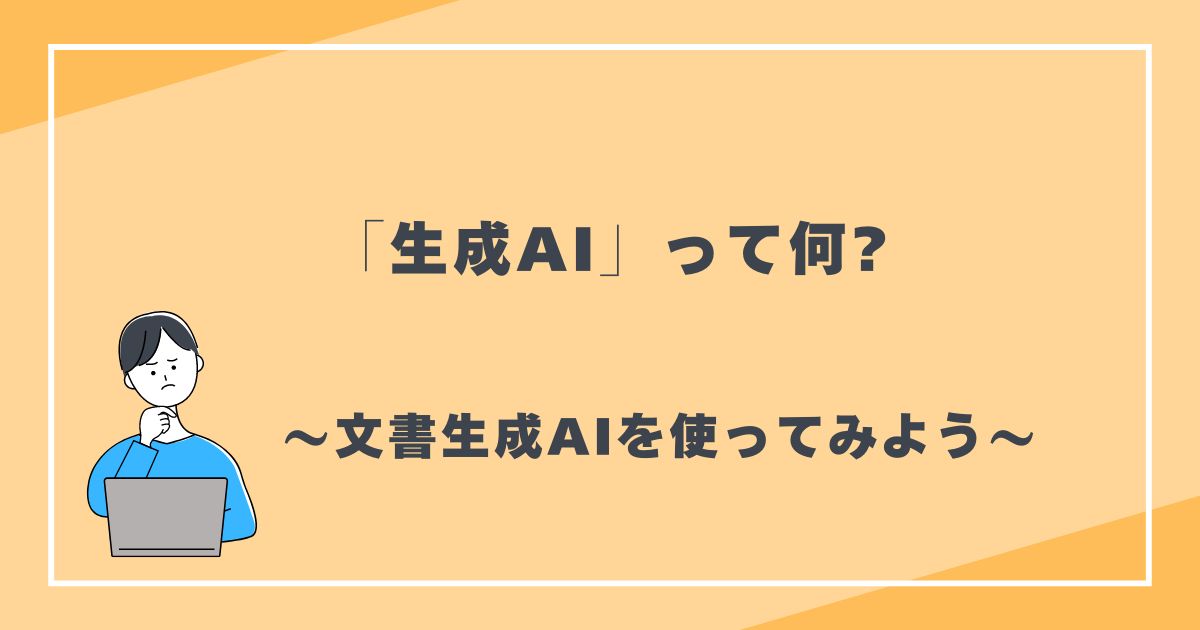リスキリングを始めたいけどどんなことにチャレンジしたら良いか分からない、ということはありませんか? この記事では初心者向けに生成AIの使い方を簡単に紹介し関連する学習方法も紹介しています。このサイトの記事をいくつか読むと自分にもできそうな何かを見つけることができるかもしれません。なお、本記事は2024年3月時点のものであり生成AIの技術進歩により記事の内容とずれが生じてくることがあります。
1 社会で急速に普及
ChatGPT(OpenAI)、Copilot(Microsoft)、Gemini(Google)などの生成AIが急速に普及しています。大企業や行政でも生成AIの活用を始めており、私たちの仕事や生活に生成AIが浸透してくるのも時間の問題です。どうしてもリスクのイメージが先行するため、生成AIの利用を先送りしようという意識が働きますが、いつまでも避けることはできない状況になってきています。こうした状況の中、リスクを正しく認識して、利用上の留意点を踏まえつつ少しずつ触りながら向き合っていくことが必要になってきます。
2 生成AIとは
生成AIは、指示を入力すると自動的にコンテンツを生成してくれるAIです。文書を生成してくれる文書生成AIのほか、画像、動画、音声などの生成に特化したAIもあります。文書生成AIは、プロンプトと言われる入力欄にユーザーが質問や指示を入力すると、生成AIが自動で文章を生成してくれます。生成される文書は、自然言語といって人間に近い言葉で文書を作成してくれることが特徴です。
3 文書生成AIの活用策
文書生成AIの活用策は、以下のような用途を含め書籍などで多く例示されています。文書生成AIの特徴を理解し自分なりの活用策を見つけていくことで可能性を広げることができます。ただし、生成された内容にはリスクがあるため回答を鵜呑みにせずご自分で評価できるようにしてください。
- 情報収集のため >>> 膨大な情報を学習しており、ユーザーの質問に対して学習した情報の中から回答を出してくれます。
- 文書作成のため >>> 文書作成の条件を与えることで、ユーザーの指示に対して条件に沿った回答を出してくれます。
- 相談相手として >>> 生成AIに役割や立場を与えることで、ユーザーの質問に対して与えられた役割や立場で回答を出してくれます。
4 文書生成AIのリスク
4-1 入力のリスク
生成AIに入力されたデータはAIの学習データとして利用されます。このため、個人情報や会社の機密情報などを生成AIに入力してしまうと第三者に流出する可能性があります。流出した情報が個人情報であれば、利用目的の範囲外になってしまったり、第三者提供になってしまうリスクがあります。また、流出した情報が会社の秘密情報であれば、秘密情報の漏えいや、NDA(秘密保持契約)の対象となる情報の場合には契約違反になってしまうリスクがあります。したがって、プロンプトに入力する際はこういったリスクがないか確認していく必要があります。
4-2 生成物のリスク
生成AIが出力した生成物のリスクとして、著作権の侵害、ハルシネーション、商用利用への抵触などがあります。著作権については生成物が他者の著作権を侵害してしまうリスク、ハルシネーションについては事実に基づかない情報が生成されるリスク、商用利用については利用規約で商用利用が認められていないリスクがあります。したがって、生成物を利用する際にはこういったリスクを一つ一つ確認していく必要があります。
5 リスクにどう対応すれば良いのか
入力した情報や、出力された生成物に対するリスクを洗い出し、チェックリストや生成AIを利用する際のルールをあらかじめ作成しておく必要があります。チェックリストのポイントとしては、情報の入力に当たり個人情報や会社の機密情報は入力しないこと、出力された生成物については回答の根拠や事実の確認を行うこと、他者の著作権を侵害していないか確認を行うこと、などです。ルールの作成については、まだ会社で生成AIの利用に関するルールを作成しているところは少ないと思いますが、管理者の知らないところで社員がすでに生成AIを利用している可能性もあるため、早めにルールを作成してリスクを低減しておくことが大切です。
6 利用規約を確認しよう
生成AIを利用する際には、利用規約の確認が求められます。利用規約は英語で書かれているものが多く、この場合、ブラウザの機能などを使って日本語に翻訳して確認することになますが、これがまた翻訳された文書の理解に苦しむことになります。それでも生成AIを利用するには利用規約を承諾していることが前提になりますので、頑張って確認しておきましょう。利用規約で確認すべき点は、禁止されていることは何か、生成物の権利は誰に帰属するのか、生成物の商用利用は可能か、入力したデータは機械学習に利用されるか、などです。
7 ルールを作っておこう
一般社団法人ディープラーニング協会が生成AIの利用ガイドラインを公表しています。これを読むとどのような点に留意したら良いかを理解することができますので、生成AIを利用する際にはぜひ一読してみてください。また、ご自身がルール作りをする立場であるなら、このガイドラインを自社に最適化して自社のルールを作ることが近道です。
8 まずは使ってみよう
まずは生成AIを実際に使ってみて、どのように生成AIが回答してくるのか体験してみてはどうでしょうか。どの生成AIを使って良いか分からない場合、MicrosoftのEdgeを使える環境であれば、Copilotで試してみてはどうでしょうか。機能に制限はありますが、サインインをせずに無料で利用することができます。ちょっと試してみるには十分だと思います。使い方は、EdgeのブラウザにCopilotのアイコンがありますので、Copilotを立ち上げて質問事項の欄(プロンプト)に質問を入力するだけです。質問は丁寧に質問してあげてください。出てくる回答をご自身で評価できる質問を入力すれば、生成AIの実力を評価できると思います。
≪プロンプト入力例≫
- 知りたいことを聞いてみる >>> 「〇〇とは何ですか」「〇〇の仕組みを教えてください」
- 相談相手になってもらう >>> 「あなたの立場は〇〇です。〇〇についてどう思いますか。」
- 調査・分析をしてみる >>> 「〇〇社のSWOT分析をしてください」
9 おすすめの学習方法
生成AIの利活用に焦点を絞って生成AIを体系的に学習できる資格は見当たりません。情報が出てきましたら掲載させていただきます。生成AIに対する質問の仕方を学ぶには今のところ書籍で十分です。ChatGPTに関する書籍が多く出ていますので、この中から読みやすい書籍を選んでプロンプトの入力例と同じように入力してみるところから始めてみてはどうでしょうか。
記事は以上です。
いかがだったでしょうか? ほかの記事も読んでみてこれだ!と思う資格を見つけてチャレンジしてみてください。