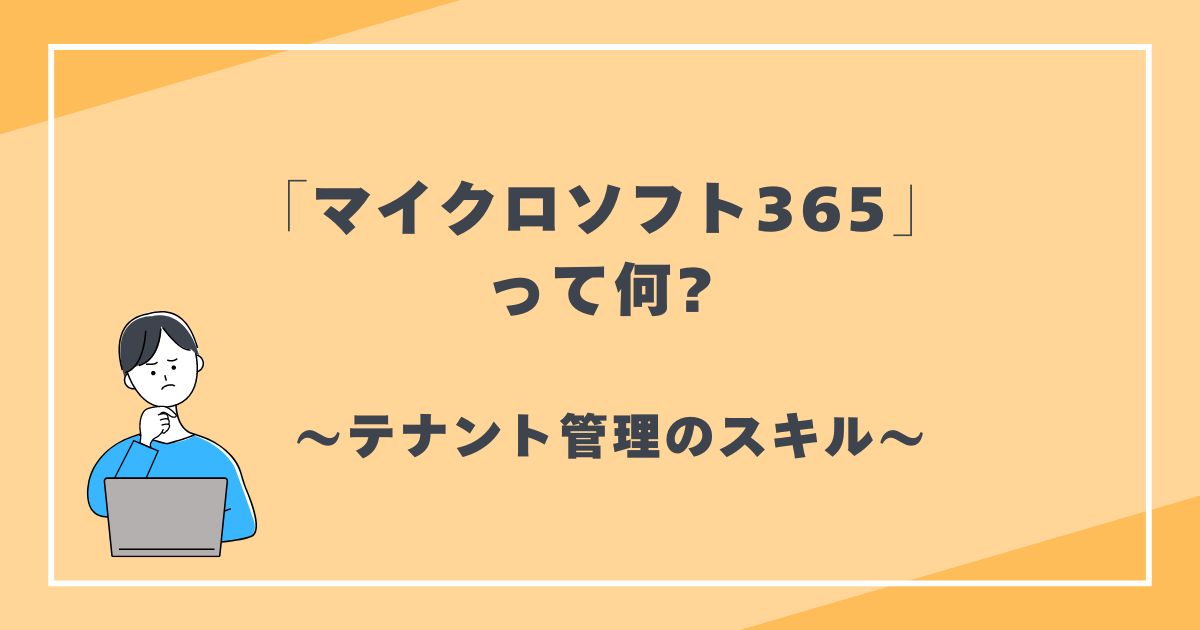Office2016やOffice2019のサポート期限が2025年10月14日で終了します。これまでボリュームライセンスによりライセンスを調達していた会社ではMicrosoft365に移行するところが多いと思います。この記事ではMicrosoft365に移行するにあたって理解しておきたいMicrosoft365について簡単に解説し、比較的学習しやすい資格を紹介します。
1 Microsoft 365とは
Microsoft 365はクラウドベースのサブスクリプションサービスです。ソフトの利用形態がクラウドであることと、対価の支払方法がサブスクリプションであることが大きな特徴です。クラウドベースではありますが、これまでと同じようにパソコンにOffice(Word、Excel、PowerPointなど)をインストールして利用することができるライセンスもあります。支払方法は買取り版がなく月額版あるいは年額版になります。
2 Office 365との違い
Microsoft365で検索するとOffice365とMicrosoft365の2つの用語が出てきます。以前はOffice365でしたが、サービスの変更に合わせてMicrosoft365に名称変更されました。
両サービスの違いとして、
「Office 365」は基本的なOffice(Word、Excel、PowerPointなど)に加えて、Teams や Share Point といったグループウェアをサブスクリプション形式で利用できるサービスであるのに対して、
「Microsoft365」は「Office 365」のサービスに加えて、WindowsOSやセキュリティ機能を備えたサブスクリプション形式のサービス
です。
「Microsoft365」にはWindowsOSやセキュリティに関する機能もありますが、Officeだけを使いたいといった場合のライセンスもありますので必要なソフトだけを選ぶことができます。
3 ライセンスの調達方法が変わります
これまでボリュームライセンスによりライセンスを調達していた会社では調達方法が変わります。ボリュームライセンスはライセンスを組織で管理できるため一度購入すると退職者があっても別のユーザーにライセンスを割り当てることができるものです。すでにこのボリュームライセンスで調達する方法が廃止されていますので、今後、組織でライセンスを調達する方法はMicrosoft 365が一般的になります。ライセンスの対価としてボリュームライセンスが買取り型であったの対してMicrosoft365は月額あるいは年額のサブスクリプションになります。
4 テナントの管理が重要です
これまでボリュームライセンスによりライセンスを調達していたときにはMicrosoftの管理画面でライセンスを管理し、パソコンにOfficeをインストールするときにライセンスキーを入力するだけでした。これに対して、Microsoft365ではまず自社のテナントを構築しなければなりません。テナントの中で、ライセンス、ユーザー、セキュリティなどを管理することになります。管理者はこのテナントの仕組みをよく理解していないとセキュリティ上の脆弱性が生じてしまうため管理者の負担が大きくなります。このテナントの仕組みを理解する方法として後述するMS-900の学習があります。
5 マイクロソフトアカウントを発行します
これまでボリュームライセンスによりライセンスを調達していたときにはマイクロソフトアカウントを発行する必要はありませんでしたが、Microsoft365に移行した場合には社員ごとにマイクロソフトアカウントを発行する必要があります。また、30日周期のライセンス認証というものがあり、ずっとオフラインでソフトを利用することができず、30日間ライセンス認証ができない場合には「機能制限付モード(読取専用)」に切り替わりOfficeの機能が制限されてしまいます。
6 ライセンスの管理が効率的になります
Microsoft365におけるライセンス管理は、利用契約したライセンスを社員ごとのマイクロソフトアカウントに紐づけることで管理します。社員のマイクロソフトアカウントごとに社員が利用しているソフトを管理できるためライセンスの管理が効率的になります。また、一括で支払う買取り型ではないため、途中でライセンスを変更あるいは解約したいといった場合には月単位あるいは年単位で利用契約を変更することができます。
7 ライセンスによってはデスクトップ版を利用できません
これまでパソコンにOfficeをインストールして利用していた場合は注意が必要です。Microsoft365はライセンスの種類が多いため違いを理解しておかないとデスクトップ版を利用できないライセンスを利用契約してしまう可能性があります。クラウド版のアプリとデスクトップ版のアプリがありますので利用したいソフトと、それがクラウド版orデスクトップ版かをよく見てライセンスを選択する必要があります。
8 Micosoft365はOfficeだけではない
Microsot365はOfficeだけではなくいろいろなソフトが提供されていますので管理者の方は一度ざっとMicrosoft365で提供されているソフトを確認してみるとよいでしょう。Teams(Web会議やチャット)やForms(アンケート作成)のほか結構使える機能があったりします。高いコストを払って別のソフトを利用しているのであればMicrosoft365に移行できないか検討してみると良いでしょう。
9 ライセンスの利用契約は慎重に
1か月あたりの料金だけを見て年額版で利用契約をする場合には注意が必要です。ライセンスを変更したい事情が出ても途中解約ができないためです。使いたいソフトが確定していない場合には、まずは使いたい機能を抽出して実現できるソフトは何か、使いたいソフトを含んでいるライセンスはどれかといった順番で検討してライセンスを選択すると良いでしょう。また、利用契約は月額版と年額版がありますので、途中でライセンスを変更する可能性がある場合には月額版で試して問題なければ年額版に切り替える方法をとると良いでしょう。
10 大企業向けと中小企業向けのライセンスがあります
Microsoft365のライセンスには、300ユーザー以下を対象とした中小企業向けのBusinessプランと、ユーザー数に制限のない大企業向けのEnterpriseプランがあります。大企業向けのEnterpriseプランには、業務内容によってさらに、フロントラインワーカー向け(現場作業向け)のプランとインフォーメーション向け(事務作業向け)のプランがあります。300ユーザー以下の中小企業でも大企業向けのライセンスを契約することは可能です。まずは、自社でどのようなソフトを利用したいか棚卸しをしてみましょう。
11 OneDriveがセットで提供される
Microsoft365はクラウドベースのツールであるため、ドキュメントを保存するOneDriveがセットで提供されます。これまでセキュリティ上、会社のデータをクラウドに保管することを禁止してきた会社にとってはOneDriveの利用を前提としたポリシーの変更を余儀なくされます。この点、コロナ禍を経てクラウドの利用が普及してきたことを考えるとクラウド利用に対する抵抗感は減っていることでしょう。
12 IDを守る
これまでオンプレをベースにしてきた会社では「守るべきもの」が社内のネットワーク内にあったためネットワークの境界に対するセキュリティ対策が重要でした。しかし、現在ではクラウドサービスが普及したことで守るべきものが社内のネットワークにない状態が当たり前になってきました。こういったクラウドベースの環境では「守るべきもの」が「ID」となり、「ID」に対するセキュリティ対策が重要になってきました。具体的には、IDを認証する際にMFA(多要素認証)を要求することでセキュリティを高めていきます。
13 まとめ
2025年10月14日にOffice2016,2019のサポート期限が終了するためMicrosoft365に移行する会社も多いかと思います。Microsoft365ではテナントを構築してテナントの中でユーザー管理、ラスセンス管理、セキュリティ管理などをしていきます。クラウドベースであるためセキュリティ対策を適切にしておかないと情報漏えいなど大きな事故を起こすリスクが残ってしまいます。このためMicrosoft365を管理するための学習をきちんとしておく必要があります。
14 おすすめの学習
MS-900 (Microsoft 365 Fundamentals)の学習が近道です。MS-900はMicrosoftが実施する認定資格の1つで、Fundamentalsは初級に位置付けられます。クラウドの一般的な知識に加え、Microsoft365に含まれる各種サービスの機能、ライセンスやサポート、セキュリティやコンプライアンスなど広範囲な内容を学習することができます。最近ではMS-900に関する書籍が出てくるなど学習しやすい環境が整ってきています。
記事は以上です。
いかがだったでしょうか? ほかの記事も読んでみてこれだ!と思う資格を見つけてチャレンジしてみてください。