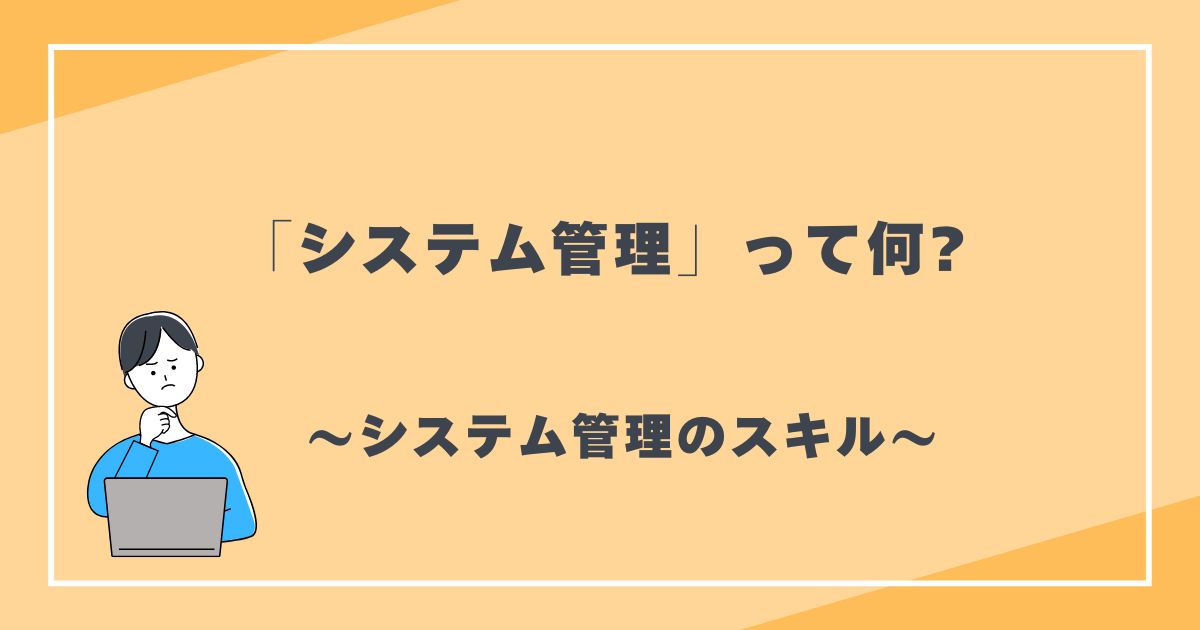リスキリングを始めたいけどどんなことにチャレンジしたら良いか分からない、ということはありませんか? この記事では初心者向けに「システム管理って何?」を簡単に解説し関連する学習も紹介しています。このサイトの記事をいくつか読むと自分にもできそうな何かを見つけることができるかもしれません。
1 はじめに
文系出身者がIT関係の仕事に就くこともありますし、これからリスキリングでIT関係の仕事をやってみたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。ここでは、IT関係の仕事のうち、会社のシステム管理者が普段どんな仕事をして社内インフラを支えているか紹介します。
2 システム管理者の仕事は幅広い
最近ではクラウドや生成AIなどが出てきていますが、社内インフラとしてベースになるものがPC、サーバー、ネットワーク、セキュリティに関するものであり、これらに関する構築、運用、障害対応などに関するスキルが必要になります。サーバーやネットワークの技術者が必要になりますが、社内の人材でカバーできなければ社外に委託することになります。障害があった場合にはどこで障害が発生しているのか切り分けの作業が必要になるため、全般的な知識が必要になります。
3 システムは社内インフラ
システムやネットワークは、電気、ガス、水道と同様に社内インフラであり、停止や遅延が起きないように予防保全に努める必要があります。仮に障害が発生して社員の皆さんが社内システムを利用できない時間が発生してしまうと会社に損失が発生してしまうことになります。したがって、予防保全や計画的な機器のリプレースを行って社内インフラを安定して提供できるようにしています。
4 どんな仕事があるか
前述したPC、サーバー、ネットワーク、セキュリティのほか、ドキュメント化、バックアップ、ライセンス管理など多岐にわたる仕事があります。
4-1 PCの管理
社員が利用するPCの管理です。新しくPCを調達する際にはコストに見合ったスペックを確定して発注。納品されたら、ハードウェアの設定、ソフトウェアの設定、ネットワークの設定、アクセス権の設定などをして社員へ配布。以後は、OSやソフトの脆弱性の対応などに伴うアップデートの配信。障害対応やお茶をこぼしてPCが動かなくなったなどといった対応もあります。PCを廃棄する際には、データを確実に消去して処分します。
4-2 サーバーの管理
サーバーのライフサイクルは前述のPCと似たようなものです。このほかサーバの特徴としては複数の社員がサーバー内のサービスを利用していることです。このため、サーバーに障害があればPCに比べて影響が大きくなります。サービスを安定稼働させるためにはサービス(ソフトウェア)一つにつきサーバー1台を充てることが望ましいところですが、サービスが多くなるとサーバーの台数も多くなってしまいます。サーバーが増えるとサーバー室内のスペースや電源の確保も必要になってきます。
限られた資源の中でサービスを提供するためには、物理的なサーバーの中に仮想的なサーバーを複数台入れるなどして物理的なサーバの台数を増やさないように工夫をしていたりします。また、最近では半導体不足からサーバーの調達が難しくなったりしていますので、災害対策なども勘案してクラウド型のサーバーを活用するといったことも考えていかなければなりません。
4-3 ネットワークの管理
社内で使っているPCやサーバー、あるいは社外のインターネットなどを利用するためにはネットワークが欠かせません。会社の規模が大きくなるとネットワークの複雑さも増して、スイッチングハブや配線ルートなどのネットワークの構成を正しく把握していないと何か障害があったときに対応が遅れてしまいます。一つの事務所だけであれば事務所内のLANだけで良いのですが、事務所が複数あればLANを結んだWANの構成も考えなければなりません。
また、ネットワークの構成に問題がなくても通信速度が遅ければサービスの処理スピードも遅くなりますので十分に通信帯域を確保できる通信回線を契約しなければなりません。最近ではコロナ禍を経てWeb会議が浸透したのでWeb会議の映像がカクカクと遅くなることは避けたいところです。
4-4 セキュリティの対策
システムやネットワークに対して幅広いセキュリティの知識が必要です。システムに関しては、PCやサーバーにウイルス対策ソフトを入れて常に最新版にアップデートしたり、ソフトウェアの脆弱性に関する情報が公表された場合には社内システムに影響がないか確認したうえでソフトウェアのバージョンアップをしたりします。
ネットワークに関しては、社外から社内ネットワークに侵入できないように入口対策を行ったり、侵入を前提として情報が外部へ流出しないように出口対策を行ったりします。社内にあるPCやサーバのうち1台でもウイルスに感染してしまうと社内ネットワークのすべてに感染してしまうおそれがあるため、社員一人一人に対してセキュリティリテラシーを教育することが不可欠です。
4-5 ドキュメントの作成
システムやネットワークを構築した際には構成図などのドキュメントを作成しておく必要があります。忙しかったりしてなかなかドキュメントの作成までたどりつくことができないこともありますが、変更があった場合も含めて、現状のドキュメントを作成しておくことで障害等があった場合に迅速に対応をすることができるようになります。PCやーバーに関しては、「ハードウェア情報」「OS情報」「ソフトウェア情報」「設定情報」など、ネットワークに関しては、「構成図」「配線図」「機器リスト」「IPアドレス管理表」などをドキュメント化しておきます。
4-6 バックアップの作成
システム障害やサイバー攻撃などによりサーバーに障害が発生し、一から復旧することになった場合には、ソフトウェアの再インストールとデータの入れ直しが必要になります。ソフトウェアの再インストールに関してはソフトウェアの販売元にお願いすればなんとか可能だとは思いますが、データの入れ直しに関してはどこも面倒みてくれません。したがって、普段から定期的にデータをバックアップしておく必要があります。全システムのデータをバックアップしようとすると作業工数の多くなりますのでシステムの重要度に応じてバックアップの頻度を考えることになります。
4-7 ライセンスの管理
ライセンスの管理を正しくしておかないとライセンス違反のリスクが発生します。ソフトウェアやサービスを利用する際にはライセンスが必要になりますが、ソフトウェアやサービスによってライセンスに対する考え方が異なります。PCの台数に応じてライセンスが必要だったり、ユーザー数に応じてライセンスが必要だったりします。ライセンスの数が必要数より少ない場合にはライセンス違反により損害賠償を請求されることもあるでしょうし、ライセンスの数が多い場合には余計な支出をしていることになり、いずれにしても会社に不要な支出を招くことになります。
5 おすすめの学習
比較的学習しやすい資格を紹介しますので、これだと思うのがあればチャレンジしてみましょう。
5-1 ITパスポート試験
経済産業省が認定する国家試験で、独立行政法人情報処理推進機構が試験を実施しています。システム管理に関することのほか、IT全般に関する基礎的な知識を体系的に学ぶことができます。
5-2 基本情報技術者試験
経済産業省が認定する国家試験で、独立行政法人情報処理推進機構が試験を実施しています。システム管理に関することのほか、情報処理に関する基本的な知識を体系的に学習することができます。
記事は以上です。
いかがだったでしょうか? ほかの記事も読んでみてこれだ!と思う資格を見つけてチャレンジしてみてください。